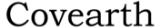ホルムアルデヒドの危険性と対策

【連載】家具がもたらす価格以外の価値
- 【第1回】 リビングを学習の場にーリビング学習のメリット・デメリット
- 【第2回】 インテリアの「色」と「素材」が持つ大きな効果
- 【第3回】 ホルムアルデヒドの危険性と対策 ←今回はココ
自然の温もりを感じさせてくれる木製家具だが、注意しておくべき点もある。それが「ホルムアルデヒド」。シリーズ最後になる本記事では、ホルムアルデヒドの危険性と対策についてご紹介する。
ホルムアルデヒドの危険性

ホルムアルデヒドとは、ヒトの粘膜を刺激し「シックハウス症候群」を引き起こす化学物質である。シックハウス症候群の症状としては、こういったものがある。
- 目がチカチカして涙が出る
- 鼻水が出る
- 喉が渇く、痛む
- 頭痛・めまい・吐き気がする
ホルムアルデヒドは接着剤に多く含まれ、室内では合板や壁紙、フローリングや天井などに使われている。家具の場合、板を張り合わせて作る「合板」の製造過程で接着剤が欠かせない。テーブルや椅子、ソファや収納棚など木製家具製品で幅広く使用されているのだ。
ホルムアルデヒドの影響度は個人差が大きく、反応の大きさは人によって様々である。ホルムアルデヒドの室内濃度指針値は、100μg/立方メートル(0.08ppm)と厚生労働省によって定められている。この濃度を超えないようにすることが大切だ。
家具は対象外?ホルムアルデヒドへの規制

平成15年に建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドを含む建築材料の使用面積の制限と機械換気の設置が義務付けられた。対象となったのは、ホルムアルデヒドを含む接着剤を使った木材や壁紙、断熱材など。
同時に、ホルムアルデヒドの放散量による区分が定められた。その区分は「F☆☆☆☆」のように表され、☆の数は1~4つでランク付けされている。☆が多いほど放散量は少なくなる。最もホルムアルデヒド放散量が少ないことを表す「F☆☆☆☆」がついた建築材料は規制対象外となり、使用面積に制限もない。この表示が、ホルムアルデヒドの少ない材料選びのカギとなるのだ。
ただ、注意しなければいけない点がある。それは、家具がこの規制の対象外である点だ。対象となるのは作り付け家具のみで、市販品は規制されていない。従って、消費者が購入する家具のホルムアルデヒド放散量を知るのは困難な状況なのだ。
実際に市販の家具には、ホルムアルデヒドが含まれているケースがある。東京都生活文化局消費生活部が収納家具を対象に行った調査によると、30検体中6検体で、室内濃度指針値を上回った。「低ホルムアルデヒド」を謳った商品でも、10検体中1検体が指針値越え。市販家具の一部にホルムアルデヒドが使用されていることが浮き彫りとなった。
ホルムアルデヒドへの対策

では、ホルムアルデヒドに触れないためにはどうすればいいのだろうか。東京都はホルムアルデヒド対策として、「家具のにおいが強く不快な場合に、どのように返品できるか購入前に確認すること」を推奨。さらに「気温の高い日に換気をしながら家具の扉や引き出しを開けて濃度を減少させること」を勧めている。
残念ながら、低価格帯の家具を中心に、指針値以上のホルムアルデヒドが使用されているケースがある。家具が規制対象外である以上、購入する商品のホルムアルデヒド含有量を知るのは極めて困難なのが現実だ。そのため、信頼できる製造業者や販売者を選ぶことや、購入した家具から刺激臭がした場合は十分に換気することなどを心がけたい。
【出典】
東京都福祉保健局「5 ホルムアルデヒドとはどんな物質ですか」
熊本市「シックハウス症候群・化学物質過敏症について」
京都府「シックハウス症候群について」
東京都生活文化局消費生活部「家具から放散される有害物質」
この記事のタグ